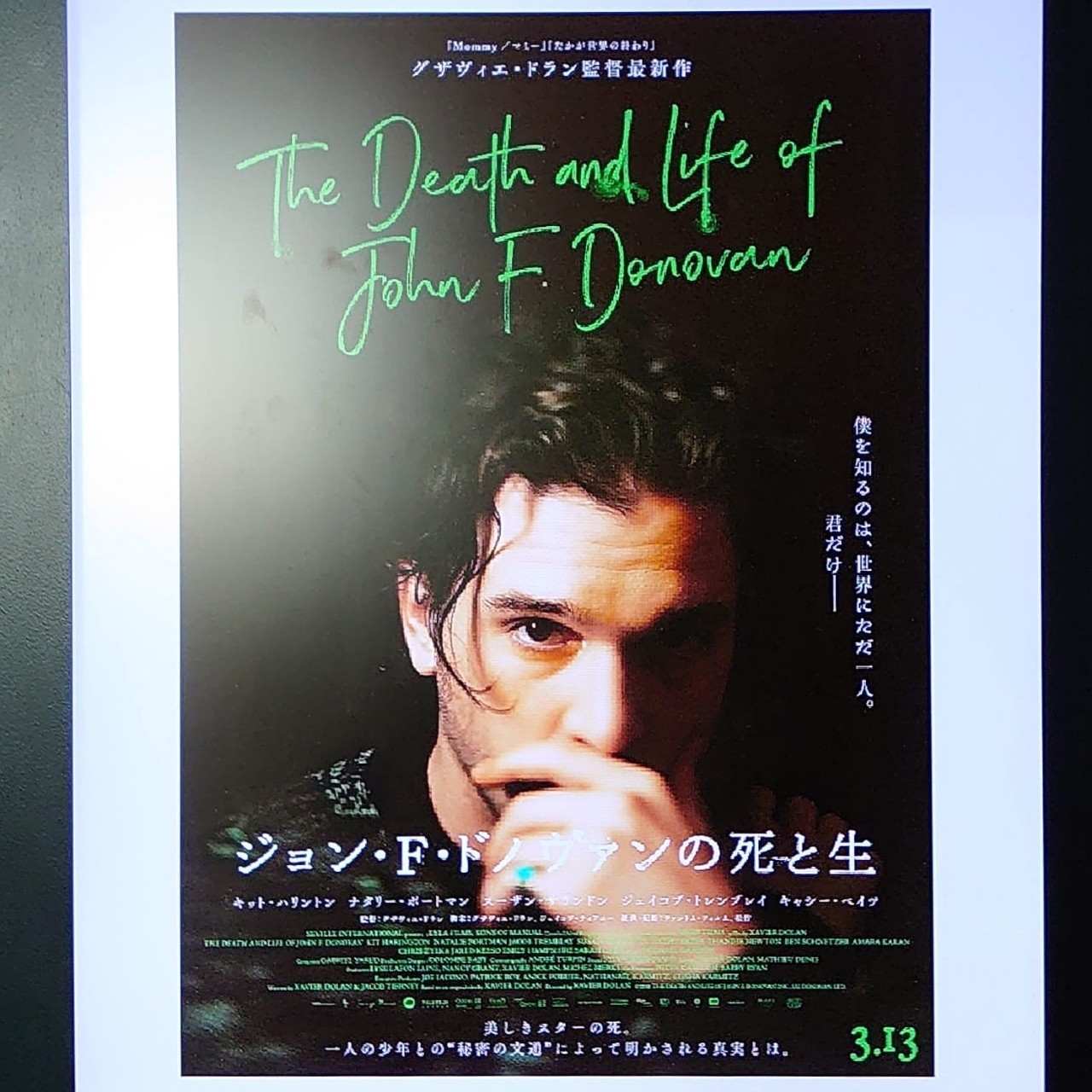【映画】ペイン・アンド・グローリー


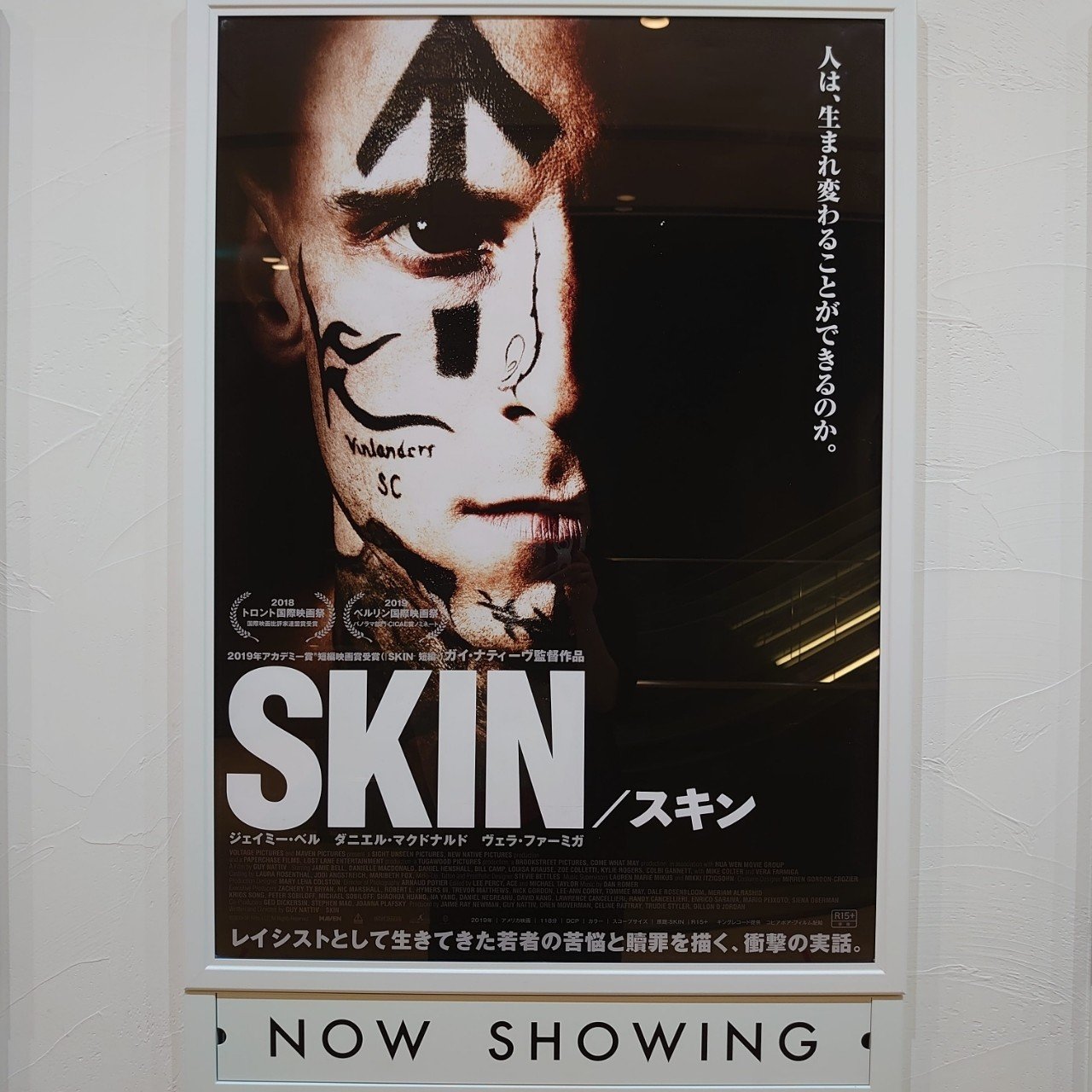


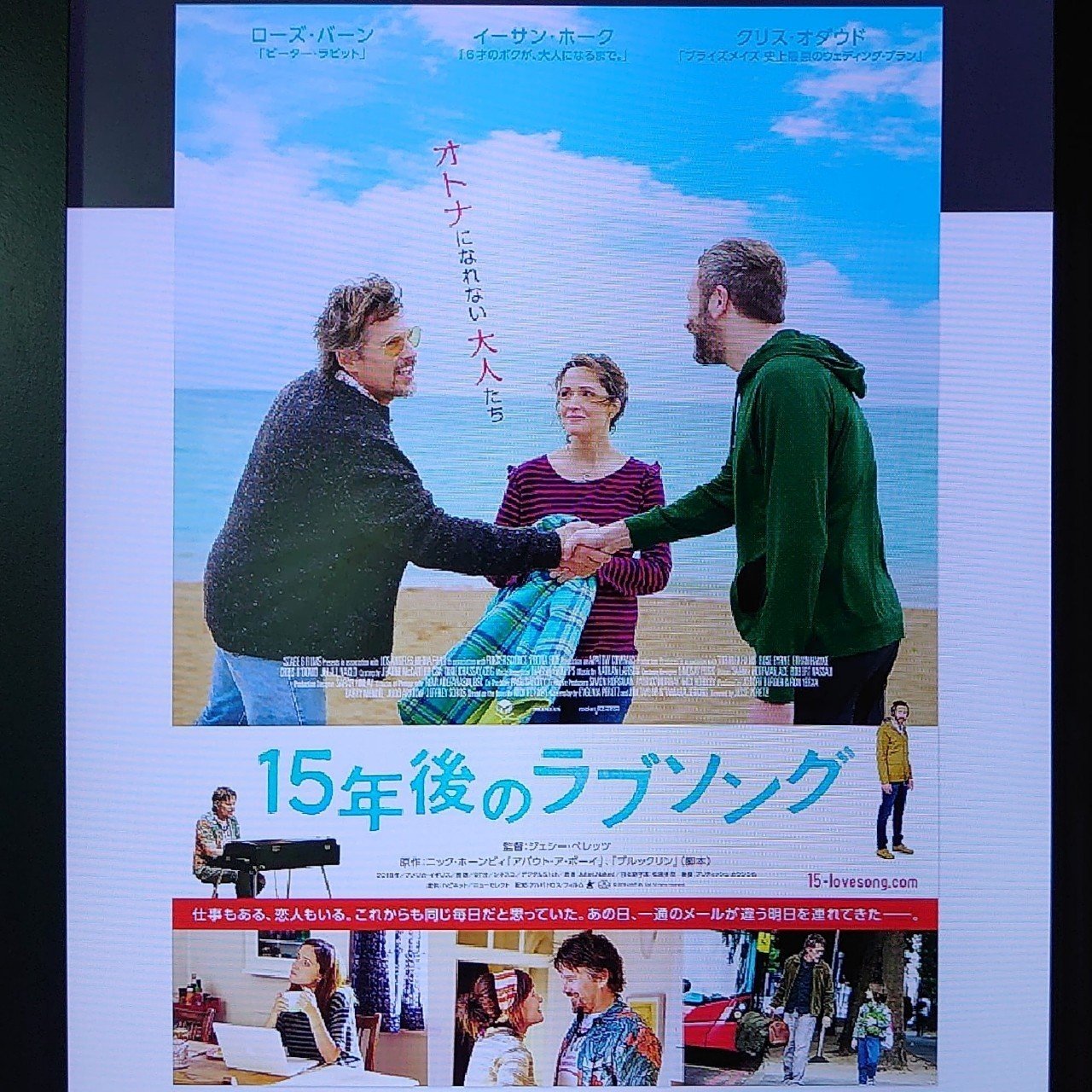
映画日誌’20-17:15年後のラブソング

COVID-19感染拡大の影響で上映延期の憂き目にあっていた本作だが、いざ公開されてみると、ミネソタ州ミネアポリス近郊で黒人男性ジョージ・フロイドが白人警察官の不適切な拘束方法によって死亡した事件をきっかけに、ブラック・ライブズ・マター(BLM)運動が大きなうねりとなって世界中にひろがっていた。何とも皮肉な話である。
なお、BLM運動は今に始まったことではなく、2013年2月にフロリダ州で黒人少年トレイボン・マーティンが白人警官ジョージ・ジマーマンに射殺された事件に端を発し、SNS上で#BlackLivesMatterというハッシュタグが拡散されたことに始まっている。自由を求めて闘った奴隷解放運動家ハリエット・タブマンが亡くなった1913年からちょうど100年が経っても、人々はまだ、闘っていなければいけないのだ。
じゃあ、アフリカ系アメリカ人の苦難はいつから始まったのか?植民地アメリカでは1619年に最初のアフリカ人奴隷の記録があるそうだ。大西洋奴隷貿易は15世紀末から19世紀半ばまで続き、1千万人以上のアフリカ人が強制的にアメリカ大陸へと送られた。
ハリエットことミンティは先祖代々奴隷であり、生まれてくる子どもも奴隷となる運命だと告げられ、絶望するところから映画が始まる。そして奴隷制度を正当化するために歪められたキリスト教の教えに従い、「鍬をしっかり掴んで、主人に仕えて働け」と歌い上げられる黒人霊歌が悲しい。
18世紀、農園で働く黒人奴隷はおよそ人間らしい扱いなど受けていなかったであろうが、そのあたりの描写はソフトだ。それどころか、10代のときに頭部に大怪我をした後遺症でナルコレプシーを患うミンティが、「神の声」を頼りに奇跡を起こしていく様子はファンタジーすら感じる。
ミンティさん大活躍の快進撃、面白かった。面白かったんだけど、拭えないコレジャナイ感。どこまでが真実なの・・・?って困惑したが、大体史実らしい。マジか。命からがら逃げ出してきた南部に戻って奴隷救出という極めて危険な作戦を幾度となく成功させ、南部戦争ではスパイとして暗躍しただけでなく、アメリカ史上初の女性指揮官として兵士を動かしている人物を描くには、いささか非合理だ。
個人的には、北部に逃亡する奴隷を匿う手助けをしていた秘密結社「地下鉄道」の背景をもう少し丁寧に描いて欲しかった。少々の物足りなさが残るが、それでも今観るに値する作品であったと思う。
「あなた達の居場所を用意しておくために私は行くのよ」——ハリエット・タブマン